オウンドメディアの失敗とは?失敗例9つや成功するためのポイントを紹介
更新日:2025.03.26
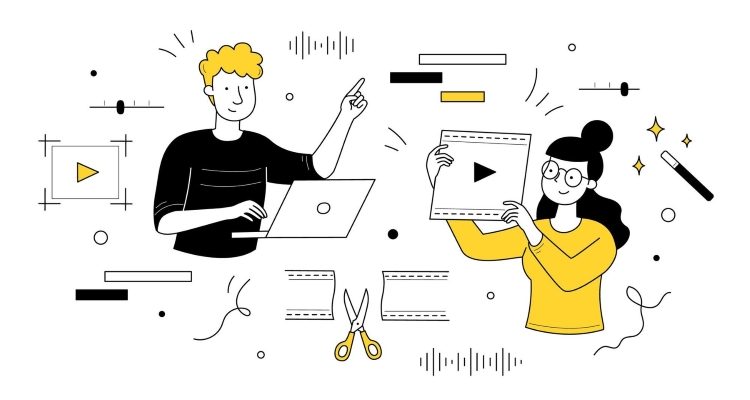
「オウンドメディアを立ち上げたものの、思うようにアクセスが伸びない…」「社内で協力が得られず、コンテンツ更新が滞ってしまった…」そのような悩みを抱えていませんか?
オウンドメディアは企業のブランド力向上やリード獲得に大きく寄与する反面、運用には地道な作業や継続が欠かせません。
そこで本記事では、オウンドメディアの失敗例を挙げながら、成功に導くためのポイントをわかりやすく解説します。「何度挑戦してもうまくいかない…」と感じている方も、ぜひ最後までお読みいただき、改善策をつかんでください。
また、株式会社hunnyでは、現在【競合調査レポート】の提供をおこなっています。貴社の競合のWeb戦略を徹底分析したレポートを【無料】でお渡しします。
Webマーケティングのプロが貴社の競合を徹底分析するので、競合に差をつけたい方は、ぜひ以下よりお申し込みください。
競合調査レポートでは、弊社独自の調査で、貴社の競合を徹底分析いたします。
- 競合サイトのパフォーマンスを詳細に分析
- SEO流入キーワードを網羅的に調査
- 効果的な広告クリエイティブを具体的に提示
さらに、弊社が実際に成果を上げた事例データも盛り込み、実践的なノウハウを公開します。
「Webマーケティングに課題を感じている」、「他社はどんな施策をおこなっているんだろう」という際にこのレポートが、現状を打破する一助となります。
目次
オウンドメディアの失敗とは
オウンドメディアの失敗とは、企業が独自に運営するウェブサイトやブログ、SNSなどで以下のような期待した成果が得られない状態を指します。
- アクセス増
- リード獲得
- ブランド向上
問題の多くは、目的の曖昧さや運用体制の不備、コンテンツの不足・質の低下など複合的に絡み合って起こることが多いです。短期間で明確な効果が出にくい性質から、途中で更新が止まり、せっかくの取り組みが無駄になってしまうケースも多々あります。
オウンドメディアの失敗例9つ
ここでは、オウンドメディアの運用で陥りがちな9つの失敗パターンを紹介します。
- 目的を明確にしないままスタートしてしまう
- メディアのターゲットが曖昧
- 短期間で成果がなければ諦めてしまう
- 社内で理解が得られない
- 運営体制が整っていない
- コンテンツの質や量が不足している
- コンテンツの更新頻度が低い
- SEO対策がおこなわれていない
- 収益化につながる導線設計がされていない
目的やターゲットの曖昧さ、コンテンツ不足、運営体制の欠如など、どれか一つでも当てはまれば成果を阻む原因となる可能性が高いでしょう。自社の状況と照らし合わせ、該当する問題点を見つけてみてください。
目的を明確にしないままスタートしてしまう
オウンドメディアは、ブランド認知度向上やリード獲得、採用強化など多様な目的に利用できます。
これらの目的をはっきり定義せずに運用を始めると、コンテンツの方向性がぶれてしまい、読者が「このサイトは何を伝えたいのだろう?」と混乱する結果になるでしょう。結果として、PV数や問い合わせ数などの指標につなげることが難しくなります。
また、目的が明確でないと、社内での合意形成や協力も得にくいです。「なんとなくSNSで話題にしたい」「有名企業のようにオウンドメディアを運営してみたい」という漠然とした理由だけでは、担当者もモチベーションを維持しづらいでしょう。
運用にかかる時間やコストが無駄になりやすく、成果につながらないケースが多いです。目的を明確化することで、記事企画や投稿計画をスムーズに進められます。
メディアのターゲットが曖昧
オウンドメディアでは、誰に向けた情報を発信するかが重要です。
ターゲットが明確になっていないと、コンテンツの方向性やトーンが散漫になり、ユーザーは興味を持ちづらいでしょう。BtoB向けの専門的な記事を書くのか、消費者に親しみやすい内容にするのか、といった基本設計が曖昧だと運用全体の軸がぶれてしまいます。
たとえば専門用語が多く使用された記事を用意しても、一般消費者向けでは難解すぎて敬遠される恐れがあります。一方で、ビジネス層に刺さる情報を提供するには、ある程度の専門性と深みが必要です。
ターゲットが誰なのか明確化しないまま運用を続けると、記事の質がまちまちになり、「読みたい記事が見当たらない」と離脱されてしまいます。ターゲット設定とペルソナの策定は、オウンドメディアの基盤といえるでしょう。
短期間で成果がなければ諦めてしまう
オウンドメディアは広告と異なり、短期的に爆発的な成果を上げるのは難しい施策です。SEO効果が安定するまで数ヶ月から半年以上かかることも珍しくなく、投稿内容がSNSや検索で拡散されるまでには時間が必要です。
ところが、いざ始めてみると「3ヶ月やっても問い合わせが増えないからやめよう」と結論づける企業が少なくありません。
本来、オウンドメディアは長期的に資産として育てる取り組みです。検索順位が上がり、ターゲット層の信頼を得てブランド認知が高まるまで粘り強く運用することで、徐々に成果が蓄積されていきます。
初期段階では、記事数やSNSシェアの基盤づくりなど地道な努力が欠かせないため、成果が見えにくくても諦めずに継続するマインドが重要です。短期間での判断は、せっかくのチャンスを無駄にしてしまう恐れがあります。
社内で理解が得られない
オウンドメディア運営には、記事執筆や取材、編集、SNS投稿など多くの業務が発生します。これらを専門担当者だけで賄うのは難しく、他部門との連携や経営陣の理解が必要になることが多いです。
しかし、社内全体で「オウンドメディアの価値」を認識していないと、協力を得られずにリソース不足に陥るケースがよく見られます。
たとえば、技術的なノウハウや商品開発の裏話など、専門知識を持つ社員のインプットがなければ記事の質は限られてしまうでしょう。営業部門の事例紹介や顧客の声なども、担当者の協力がないと集められません。
経営者レベルで「オウンドメディアでブランディングを強化する」という目標が共有されていなければ「本業とは関係ない」と見なされ、優先度が低くなる可能性もあります。
運営体制が整っていない
オウンドメディアを継続的に更新するには、記事の企画から執筆・編集、公開スケジュールの管理、SNS拡散など多岐にわたるタスクが生じます。
これらを担当するチーム体制が明確でないと、誰がどの工程を担当すべきか不明瞭となり、記事公開の遅延や内容の重複、品質のばらつきが発生しやすくなります。また、スケジュール管理ツールやタスク管理ツールを使っていない場合、締め切りが守られずに読者をがっかりさせることもあるでしょう。
定期ミーティングの実施や役割分担を明確化して、運営に関わる全員が連携できる仕組みを整えるのが理想です。特に社内外のライターやデザイナーを起用する場合は、コンテンツごとの進捗に関して追える体制を構築しないと、更新頻度が低下してしまう一因となります。
オウンドメディアの運営体制を整えるために外部に依頼したい場合の費用を確認したい方は、以下の記事をご確認ください。
【関連記事】ホームページ制作の費用相場を種類別・依頼先別に紹介!安く抑える3つの方法も
コンテンツの質や量が不足している
オウンドメディアで求められるのは、読者が「読みたい」「役立ちそう」と思うような質の高いコンテンツです。
記事のテーマが薄かったり、情報が古かったりすると、検索順位も上がりにくく、読者の満足度が低いためリピートやシェアにもつながりません。また、そもそもの記事本数が不足していると、サイトへの訪問機会やキーワードの網羅性が低く、アクセス数を伸ばすのは難しいでしょう。
「質と量」の両立が理想なものの、現実的にはリソースに限りがあります。外部ライターの活用や長期的な記事制作計画を立てるなど、コンテンツ制作体制を確保する工夫が必要です。
読み物としての面白さ、専門知識の深さ、ビジュアル面の魅力など、多角的にクオリティを高めていくことで、徐々に読者の信頼を得られるようになります。
コンテンツの更新頻度が低い
内容がよくても、更新が止まったままのメディアではリピーターを育成しにくいです。
定期的に新しい記事が追加されないと「このサイトは動いていないのかな」と思われ、検索エンジンの評価も下がります。検索クローラーが訪れた際に新規コンテンツや更新が見られなければ、検索順位を上げる要素になりにくいため、SEO対策の面からも不利になります。
逆に、更新頻度が高いほどSNSでシェアされるチャンスが増え、ユーザーが「また来たい」と思える仕組みを作りやすいです。
ただし、頻度重視で品質を犠牲にすると逆効果になる可能性があるため、チーム体制とバランスを考慮しながら週1回や月数本など適切なペースを設定しましょう。読者に更新スケジュールを告知することで、期待感や待ち遠しさを醸成するのも効果的です。
SEO対策がおこなわれていない
オウンドメディアの記事は、検索エンジン経由での流入が大きな柱となります。
しかし、タイトルや見出し、本文内のキーワード設計、内部リンクの最適化など、SEO対策を一切おこなっていない場合、いくらよい内容でも検索結果に表示されにくいです。結果として、潜在顧客の目に触れないまま埋もれてしまう恐れがあります。
キーワードリサーチやメタ情報の設定、モバイルフレンドリー対応など、基本的なSEO施策は必須です。検索意図を満たしたコンテンツ制作など、読者満足度を高める施策も必要です。
SEOについて意識しないまま記事を書いていると、アクセスが伸びずにモチベーションが低下し、コンテンツ更新が停止してしまう悪循環も生まれます。せっかくの良質な記事を無駄にしないためにも、SEOの視点を忘れずに運用することが大切です。
収益化につながる導線設計がされていない
オウンドメディアは単に情報発信するだけでなく、商品販売やサービス申し込み、問い合わせなど企業の収益につなげる目的を持つことが一般的です。
しかし、サイト内に購入や問い合わせへの導線が用意されていない場合、どれだけアクセスが増えても実際の売上やリード獲得に結びつかない可能性が高いでしょう。
「記事の最後に問い合わせフォームへのリンクを設置する」「関連記事からECサイトへ誘導する」など、読者の行動につながる仕組みを作るのがポイントです。
明確なCTA(コールトゥアクション)を設定し、ユーザーがスムーズに次のアクションへ移れるかどうかを意識しましょう。収益化に結びつく導線が不十分だと、更新コストばかりかかって成果を感じられず、運用が継続しづらい原因にもなります。
オウンドメディアで成功するためのポイント5つ
失敗例を踏まえたうえで、オウンドメディアを成功に導くための秘訣を5つ紹介します。
- 目的・目標を決めておく
- ツールを使って現在の課題を明確にする
- リソースを確保し運営体制を整える
- 質の高いコンテンツを継続的に更新する
- プロのサポートを受ける
これらのポイントを押さえておけば、着実に成果を得やすくなるでしょう。
目的・目標を決めておく
オウンドメディアを立ち上げる前に「何を達成したいのか」を明確にすることが最重要です。ブランド力を高めたいのか、リード(見込み客)を獲得したいのか、採用ブランディングを強化したいのか、目的によって記事の内容や運用方針は大きく変わります。
目標設定をする際には、具体的なKPI(Key Performance Indicator)を設定しておくのがおすすめです。たとえば「月間PV数10,000を目指す」「月間問い合わせ数を100件にする」など、数値目標があれば運用状況を客観的に評価し、適切な改善施策を打ちやすくなります。
また、目標を社内に共有することで協力体制を得やすくなり、部署横断的なサポートも期待できるでしょう。
ツールを使って現在の課題を明確にする
オウンドメディアの現状を把握するには、アクセス解析ツールやSEOツール、キーワード調査ツールなどを活用し、定量的なデータで課題を洗い出すことが大切です。
ページビュー(PV)やユニークユーザー(UU)、滞在時間、直帰率などの指標をチェックすることで、読者がどのページに興味を持ち、どこで離脱しているかを把握可能です。特にGoogleアナリティクスやサーチコンソールは無料でも高機能であり、導入しやすいツールの代表格といえるでしょう。
検索キーワードや流入経路の分析をおこなえば、コンテンツの方向性が読者ニーズにあっているか検討できます。また、有料のSEO解析ツールを活用すると、競合サイトのキーワード対策や被リンク状況もリサーチできるため、自社との差別化ポイントを見つけやすくなるでしょう。
ツールの活用がオウンドメディア成功への近道です。
株式会社hunnyは、SEO対策、Web広告、SNS運用など、Webマーケティングにおけるさまざまな分野に精通しています。
Webマーケティングでお困りの際は株式会社hunnyの【競合調査レポート】を見ることで、貴社の強みや新たな視点が見えてきます。以下のボタンから【競合調査レポート】をお申し込みください。
リソースを確保し運営体制を整える
オウンドメディアは長期的な運用が鍵です。担当者が1〜2人しかおらず他の業務と兼任していると、記事制作やSNS投稿、分析作業が滞りがちになるリスクがあります。
そこで、社内のライターやデザイナーを巻き込んだり、外部ライターを採用したりといったリソース確保が必須です。また、運営体制として編集長やディレクター、ライター、SNS担当など役割分担を明確にし、スケジュール管理ツールを使ってプロセスを可視化することも大切です。
定期的なミーティングをおこない、記事の企画や公開スケジュールを共有しながら進めると、計画的にコンテンツを増やせます。運営体制が不十分だと、更新が滞って読者離れを招きやすいため、早めに適切なチーム編成を整えましょう。
質の高いコンテンツを継続的に更新する
オウンドメディアを成功させる最大のポイントは「質の高いコンテンツ」を「継続的」に提供することです。
読者が求める情報を深掘りした記事や専門家の見解を交えた有益なコンテンツが発信できれば、検索エンジンやSNS経由で自然と集客が増え、長く読まれる資産となります。
しかし、一度よい記事を書いても更新が止まってしまえば読者の関心は薄れ、検索順位も下がりやすいです。数か月かけて積み上げたアクセスやファンを維持するには、少なくとも週1回など決まった頻度での記事公開を目指したいところです。
スケジュールに追われて品質を落とすのは避けたいので、余力がないと感じたら外部ライターの活用や記事数を調整してでも「継続できる仕組み」を優先してください。
プロのサポートを受ける
オウンドメディアの運営には、記事制作だけでなくSEO対策やSNS連動、効果測定など専門性が必要となる領域が多々あります。
社内リソースだけで賄おうとすると、ノウハウ不足で回り道をしたり、最適解を見つけるまでに時間がかかったりするケースもあるでしょう。そのため、必要に応じてプロのサポートを受ける選択肢も検討しましょう。
たとえば、以下のように部分的なアウトソースをすれば、社内リソースを無駄に消耗せずに済みます。
- 外部ライターや編集者を雇って記事制作のクオリティを高める
- SEOコンサルタントにサイト構造やキーワード設計を依頼する
- SNS運用を代理店に任せる
また、オウンドメディア全体を包括的にサポートしてくれるサービスもあり、運用ノウハウの蓄積やPDCAサイクルの高速化につながるため、検討する価値が高いです。
株式会社hunnyならオウンドメディアの運用から分析まで徹底サポート
「オウンドメディアの運用を本格的に始めたいがリソースが足りない…」「何度試しても失敗続きで改善策がわからない…」という企業もあるでしょう。
そのような場合は、株式会社hunnyのサポートを活用するのも有効です。
広告運用やSEO対策など幅広いデジタルマーケティングを経験豊富なスタッフが一括で担当し、効果的なコンテンツ戦略を構築してくれます。競合調査を無料でおこない、具体的なレポートを提出してくれる点も魅力的です。
Webマーケティングでお困りの際は株式会社hunnyの【競合調査レポート】を見ることで、貴社の強みや新たな視点が見えてきます。以下のボタンから【競合調査レポート】をお申し込みください。
まとめ
オウンドメディアで失敗する企業に共通するのは、目的や運営体制の曖昧さ、更新頻度の低下など、基本的なポイントを押さえていないことが多いです。
成功のためには、明確な目的設定やターゲットの把握、継続的なコンテンツ更新、SEO対策、収益化導線の設計などを徹底する必要があります。
もし社内リソースが限られている場合は、hunnyのような専門家に依頼することで、遠回りせずに着実な成果を得られるでしょう。ぜひ本記事を参考に、オウンドメディアの失敗を避けてビジネスを加速させてください。



